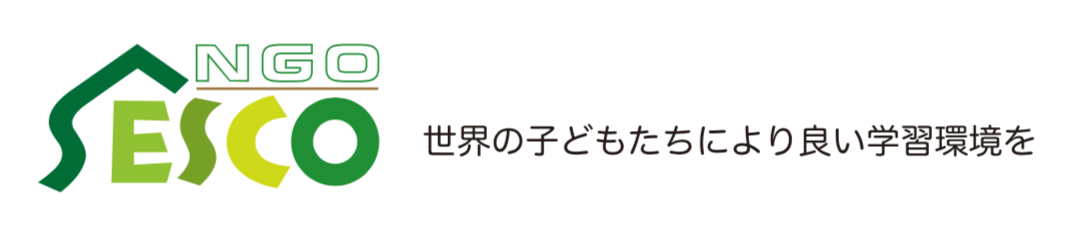NGO SESCO 論考 NO. 25 号 喪失した3本の柱
― 西部邁・池内紀・石原慎太郎 ―
去る2月1日石原慎太郎氏が逝去された。喪失感が大きい。西部邁の論考、池内紀のエッセイ、そして石原慎太郎の文学は、我が人生にとって憧れと教訓を与えた同時代の傑物。唯一残された最後の人であった。過去に取り上げた書評から一部を削除修正再録した。
西部邁 著 『保守の真髄―老酔狂で語る文明の紊乱』
西部邁氏が「自裁死」した。2018年1月21日。氏は評者と同年1939年生まれの78歳。左翼過激派時代を除き新聞、雑誌、著書、「朝まで生テレビ!」を 通じて後年の近代保守主義の知識や論理には圧倒された。本書は4章にまとめられた「遺書」である。1.文明に霜が下り雪が降るとき 2.民主主義は白魔術 3.貨幣は「戦の女神」 4.「シジフォス」の営みは国家においてこそ 歴史と国家のコモンセンスが問われる中、登場する哲学者、思想家、政治家など多数。マッキャヴェッリ、ヴィーコ、福沢諭吉、ヴェブレン、中江兆民、ケインズ、ガンディ、チェスタトンなど。
・「紊乱」について述べた後、自身の言う述者(著者)は「・・G.K.チェスタトンがF.ニーチェに対していったこと、『狂気に一抹の魅力があることを認めぬわけではないが、それを認めるためにもこちとらが正気でなければならぬ』を座右の銘として生きてきた述者としては、正気が狂気と見えることこそ現代文明が紊乱の極みに近づいていることの証拠ではないか」
・「人生の最大限綱領は一人の良い女、一人の良い友、一冊の良い書物そして一個の良い思い出」の「人生を良いものにする四点セット」を語り続けた。「人は必ず死ぬ。時代は必ず変わる。その避けようのない行程の中で、何かを求めて何事も得ずに死んでいく人々の膨大な思い出の数々、それが歴史を支えるのである。」
・人工死に瀕するほかない状況で病院死と自裁死のいずれをとるか「自然死と呼ばれているもののほとんどは、実は偽装なのであって、彼らの最後は病院に運ばれて治療や手術を受けつつ死んでいくことなのである。換言すれば『病院死』。瀕死者にとっての病院は、露骨にいうと、死体製造(および処理)工場にすぎない。」「病院死を選びたくない。おのれの生の最期を他人に命令されたり弄り回されたくない。病院死を非難するものではないが。」ナチュラル・デューティだと考える。
ノンフィクション作家、保坂正康が「明治36年の旧制一高生、藤村操による日光・華厳の滝への投身自殺。昭和2年、芥川龍之介の薬物自殺。昭和24年の東大生で光クラブの山崎晃嗣の薬物自殺。そして昭和45年、三島由紀夫の割腹自殺。これらの自殺は、単に個人の自殺というより、時代そのものが演じた死だ。」「西部氏をこの系譜に連ねての歴史に刻む言葉は、『近代の学問、理論を前にさまよえる日本人。伝統倫理に復せよ』」と。この「死」を歴史の文脈でとらえる論考に全く納得である。西部さん さようなら。
―――――――――――――――――――――――――――――
池内紀 著 『記憶の海辺 一つの同時代史』
2019年8月30日に亡くなった池内紀『記憶の海辺』。著者は1940年生まれ、ドイツ文学者・エッセイスト。評者(深尾)より一歳年下で同時代を生き親和性が強い。ドイツ、旅、人生観、居酒屋などがキーワードに随分教えられる事が多かった。「10歳のときの朝鮮戦争から、カフカ訳を終えた60歳までをたどっている。おぼつかない自分の人生の軌跡をたどって、何を実証しょうとしたのだろう。
念願としたのは私的な記録を通した時代とのかかわりだった。同時代の精神的な軌跡の証立てだった。一つの軽はずみな生きものを、うっかりわが身に引き受けて、当然のことながら悪銭苦闘した。(中略)自分に許されたひとめぐりの人生の輪が、あきらかにあとわずかで閉じようとしている。そのまぎわに何とか書き終えた。」とあとがきに書かれている。
目次。はじめに ―「糞石」のことⅠ 三八度線 ― 戦争は儲かる ネヴァーランド―「もはや“戦後”ではない」 「神様のノラクラ者」― ある猶予期間 「プラハの春」― 才能の行方 赤い靴と白い靴― フラウ・プロノルドのことⅡ 港の見える丘 ― 小林太市郎のこと 東京地図帳 ― 日本シリーズ第四戦 ビリヤードの球とトカゲの尻尾― 風刺の文学 中心と辺境 ― ウイーンの世紀末 メフィストの小旅行 ― 東京大学 一人二役 ― 翻訳についてⅢ レニ会見記 ―「運命の星」について G・グラス大いに語る ― 沈黙の罪 一日 の王 ― 山と川と海 「こんばんは、ゲーテさん」―『ファウスト』訳 海辺のカフカ ― つとめを終えること おわりに ― I・O氏の生活と意見・姫路市で生まれた。「へんてこな『昭和の子』である。戦争が終わったとき、まだほ
んのハナたらしであって、戦中の記憶はない。」
・大学卒業後、一流企業に就職した同窓と銀座で出くわし励まされた。が、「私は別に自分が落伍者とも、遅れをとったとも考えていなかった。サラリーマンになりたくない。生活は安定するだろうが、すべての時間をサラリーのために取られてしまうのは、自分を裏切るような気がした。」確かに著者は自己を持っていた。
・1967年7月オーストリア政府奨学金を得てウイーン大学へ。現地の法学部学生・エーリッヒと「言葉の交換」としてドイツ語のテキストはカール・クラウスの『人類最期の日々』、日本語は石川淳の小説『焼け跡のイエス』。双方が訳文を作って読み合わせをする。充実した青春が羨ましい。
・1986年8月、チェコ事件に遭遇する。留学生の見た「プラハの春」を加藤周一に乞われて報告している。「作家、音楽家、芸術家、学者などは、幸福の絶頂でした。」
45歳のとき、東大の教師になり55歳で東大教授を辞めた。3つの予定を立てた。1.カフカの小説をひとりで全部訳す。2.北から南まで好きな山に登る。3なるたけモノを持たない生活をする。「カフカの小説の全訳に6年かかった。やり終えたとき、版元が加わっているタブロイド版のPR紙に、おどけをまじえて書いた、『全6巻・総頁数2400・400字詰原稿用紙4800枚・200字詰をあてたので総数9600枚』。
「とにかく全力投球した。そして多くを学び、多くに気がつき、多くの原稿用紙を消費して、視力を大きく失った』」各章の冒頭に年代記を掲げ、その時代に筆者は何を考え、何をしたか。55歳で筆一本の生活に入ったのも、権威を嫌った人らしい。人と群れることを好まず「仕事の切れ目が縁の切れ目」とうそぶいたが人への優しさは欠かさない。なすべき仕事をし終え、静かに筆を置いて旅立っていった。同時代を生きた評者も人生を振り返りながら哀惜の念と共に熟読した。会者定離。
石原慎太郎 著 『老いてこそ生き甲斐』
筆者の7歳年長の巨人、石原慎太郎(1932年生まれ)作品は永年結構読んできた。近年は昔話、穏やかなものが増えてきた印象が強い。目次。1「老い」の定義、2親しい人間の死、3長生きの是非、4肉体的挑戦、5執着の断絶、6過去への郷愁、7人生の配当,8老いたる者の責任。
「老化にともない誰にでも現れる不可避な現象は病気ではなしに『生理的老化』と呼ばれる現象で、皮膚の皺、染み、老眼、白内障、難聴、骨量減、動脈硬化、筋肉量の減少など枚挙に遑がありません。」「老いの先には必ず死が待ち受けています。そして死については誰も知らない。故に死は人間にとって最後の未知、未来ということです」。「自分以外の人間の死は皮肉なことに今こうして生きていて他人の訃報を聞き取った己との対比で、ある活力を与えてくれるものです。それは人間の備えたエゴの醜い発露かもしれないが、皮肉な真実、事実でもある。他者の死との比較で確認される己の実在への皮肉な感動は、新しいエネルギーをもたらしてくれる。」「老いに対する立ち向かいの術は、まず何よりも慨嘆しないことです。つまりこの自分には必ず明日がある」。
著者は呆気ない程まともに「老い」を見つめている。この「平凡」の中の「非凡」を注視した。「人間は誰しも必ず死ぬのです。それまでの老いをいかに生き抜くかが、その人生の本当の意味をなすことになるのです。」三島由紀夫、川端康成、江藤淳、西部邁などの自殺に対し石原慎太郎の「老いと戦う」姿勢に全く同感。「老いてはいても常に新しい生き甲斐を見出し、与えられた天寿を全うすることこそが人生の見事な完成になり得るはずです。」「気品を備えて生き抜く。」これこそ我が目標だ。合掌